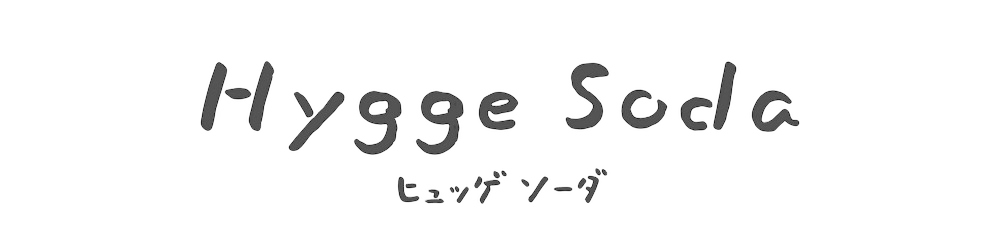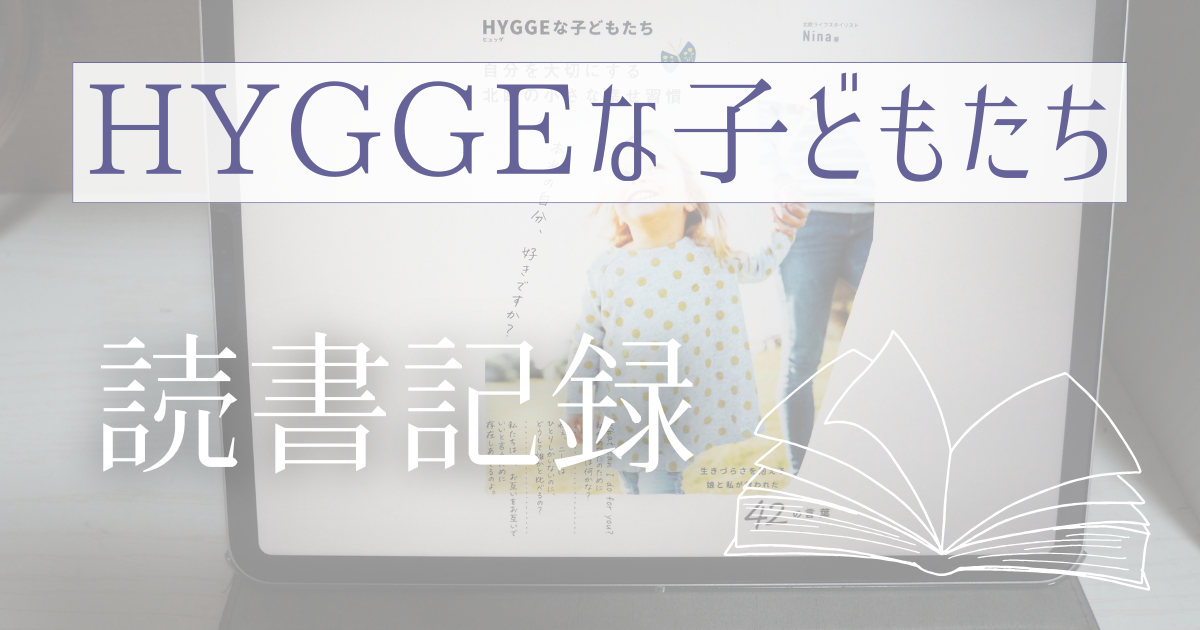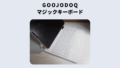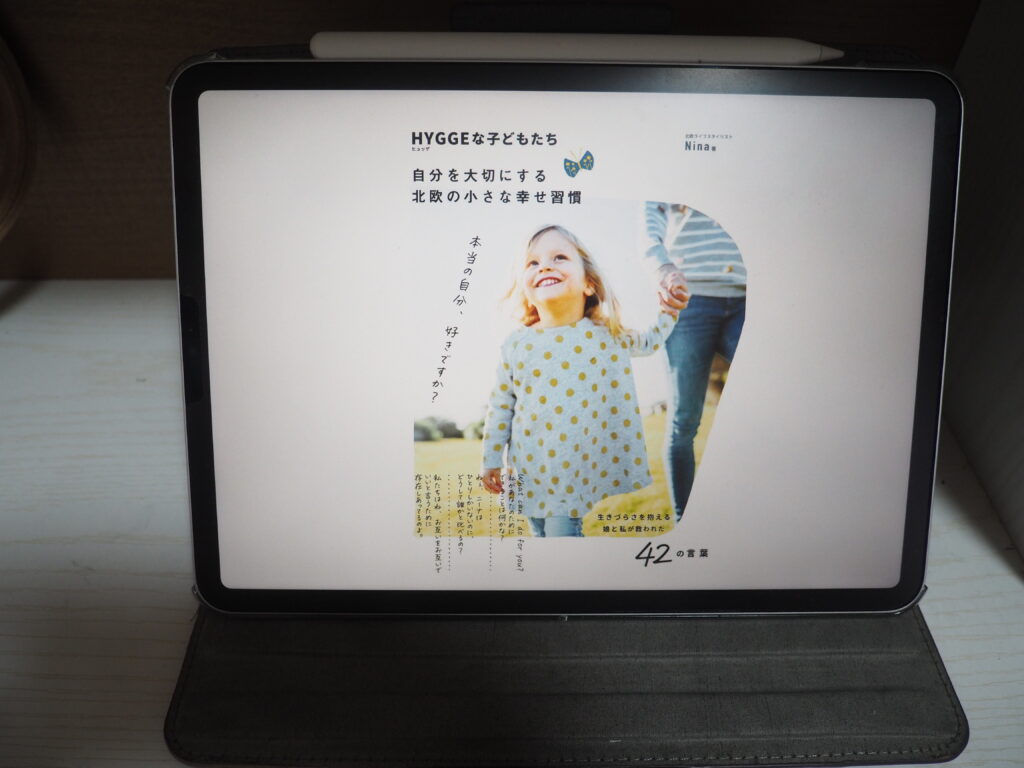
北欧文化の本を読んでいると、日本に暮らす私とは少し違う価値観に出会うことがあります。
でもその考え方はとてもシンプルで、「本来、人ってそうあるべきものだよなぁ」と思うことばかりで、心にすっと入ってきます。
今回は「HYGGEな子どもたち」から、特に印象に残った「寄付」「子どもの片付け」「大切にするもの」について紹介します。
寄付が当たり前の社会

北欧では、誕生日プレゼントを寄付する人が多いということに驚きました。
どこの団体に寄付したのかを話すこともあれば、なぜそこを選んだのか理由を伝えることもあるそうです。
大人はだけでなく、子どもも真剣に誰かを思って寄付していること。
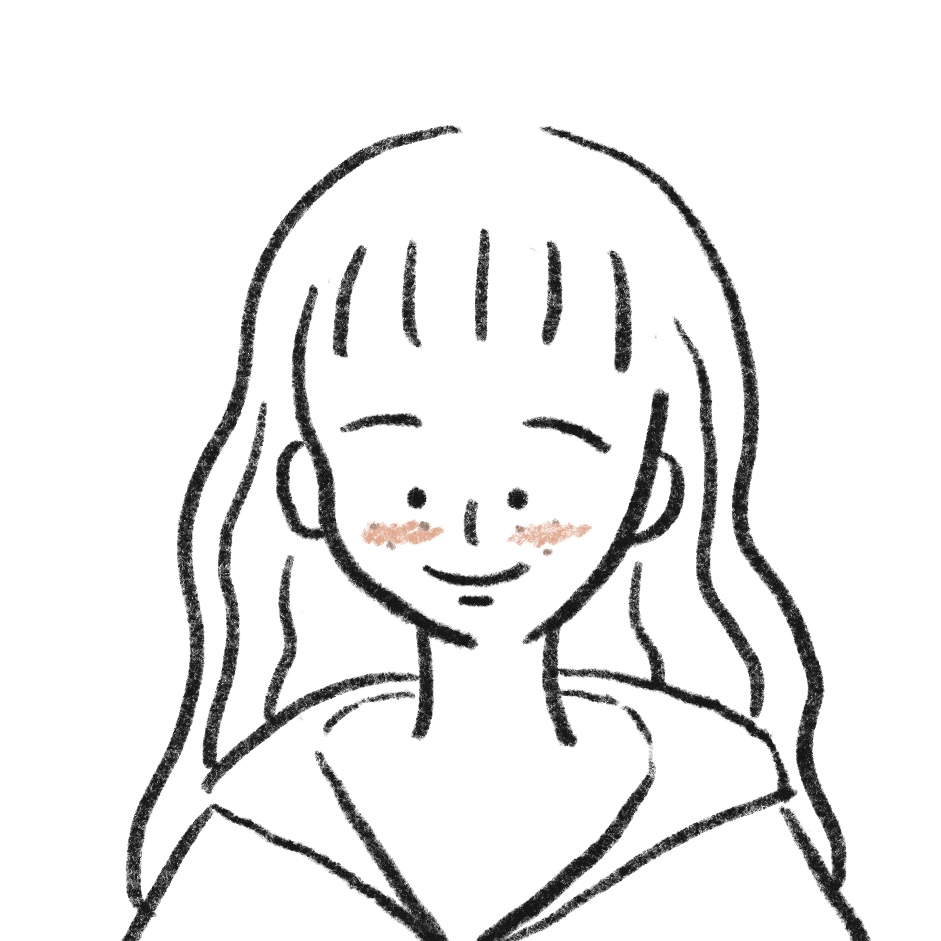
親の背中を見るとは、そういうことなんだなあと改めて学びました。
そして北欧らしいのが「寄付した」という行為を誇る気持ちではなく、価値観を共有する自然なコミュニケーションがあるということ。
それから私自身も、暮らしの中で寄付について考えることが増えました。
テレビで流れる貧困地域の映像を見て、小学生の息子が「この子はなんで服着てないの?」「虫嫌じゃないのかな?」と質問してきたことがありました。
中学生の娘は、弟がご飯を残すと「食べものがない国もあるんだよ?」と声をかけることもあります。
そんなとき、私も言葉で説明するだけでなく、誕生日プレゼントでなくても、家にある不用品を寄付したり、少しずつ行動を起こしたりすることで、子どもたちが「なぜ?」と感じたことが、世界とつながる小さなきっかけになる気がします。
子どもの片付けを尊重する
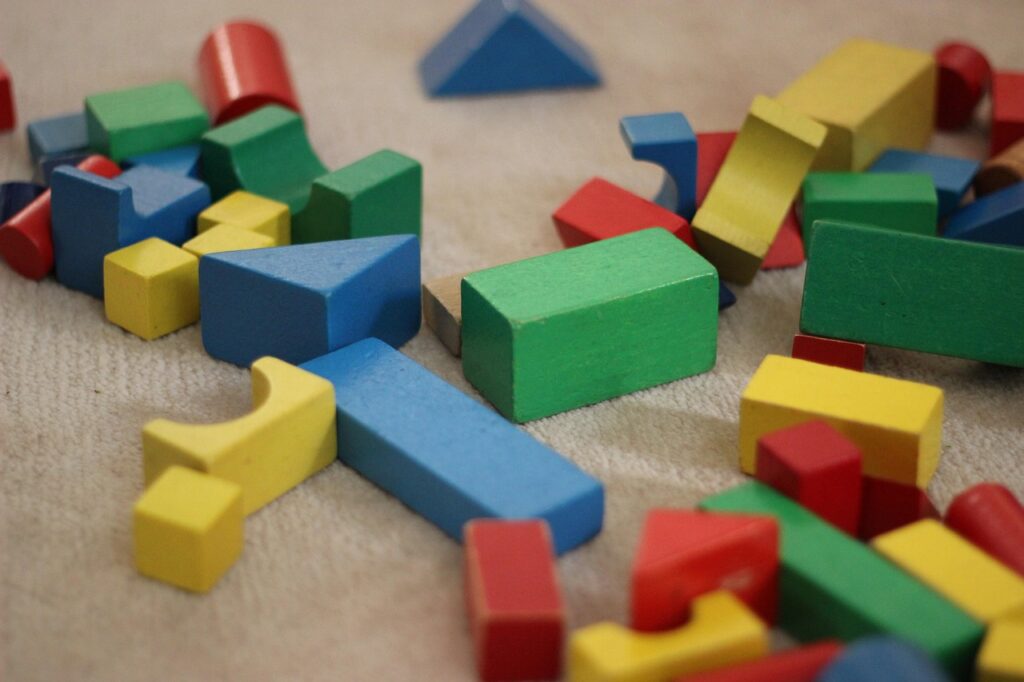
子どもが自分で片付けをすると、どうしても雑になりがちです。
大人の目から見ると「もっときれいに整えてあげたい」と思ってしまいますが、北欧ではそこで手を加えないことを大切にしているそうです。
なぜなら、大人がやり直すことで「これではいけない」と子どもに伝えてしまうから。
ハッとさせられました。
私はつい「ここに入れてね」「まだ散らかってるよ?」と口を出してしまうタイプなのですが、この考え方を知ってから“これがこの子のベスト”“よくできました!”と思えるようになりました。
大切なのは整った棚よりも、子どもが「自分でやった!」と感じられる達成感を、暮らしの中で尊重することの大切さを教えてもらった気がします。
いちばん大切なのは「自分」と「すべての子どもたち」

北欧では「まず自分自身を大切にする」ことが基本にあります。
その次に「すべての子どもたちを守る」という考え方。
これは“自分を犠牲にしてまで誰かのために尽くす”という価値観とは少し違います。
子育てをしていると、自分のことはつい後回しにしがちで、私も「自分を優先するなんてわがままかな」と感じることがあります。
それも日々の積み重ねで、塵も積もれば山となり、心が揺らぐことが本当に何度もありました。
でも“自分を大切にすることは、子どもを大切にすることにつながる”という北欧の考えに出会ってから、気持ちが少し楽になりました。
おわりに

北欧の暮らしに根付いた考え方はとてもシンプルで、日本で暮らす私の日常にもすっと取り入れられるものばかりでした。
「誰かのために寄付する」「子どものやり方をそのまま尊重する」「まず自分を大切にする」、この3つ以外にも学びが本当にたくさんあります!
劇的な変化ではなく、小さな意識の積み重ねが日々を心地よくしてくれる。そんな大切なことを、この本は教えてくれました。
子育てや仕事で悩んだとき、立ち止まって「HYGGEなこどもたち」を読み返すと、そっと背中を押してくれるヒントが見つかる、私にとって宝物のような一冊です。